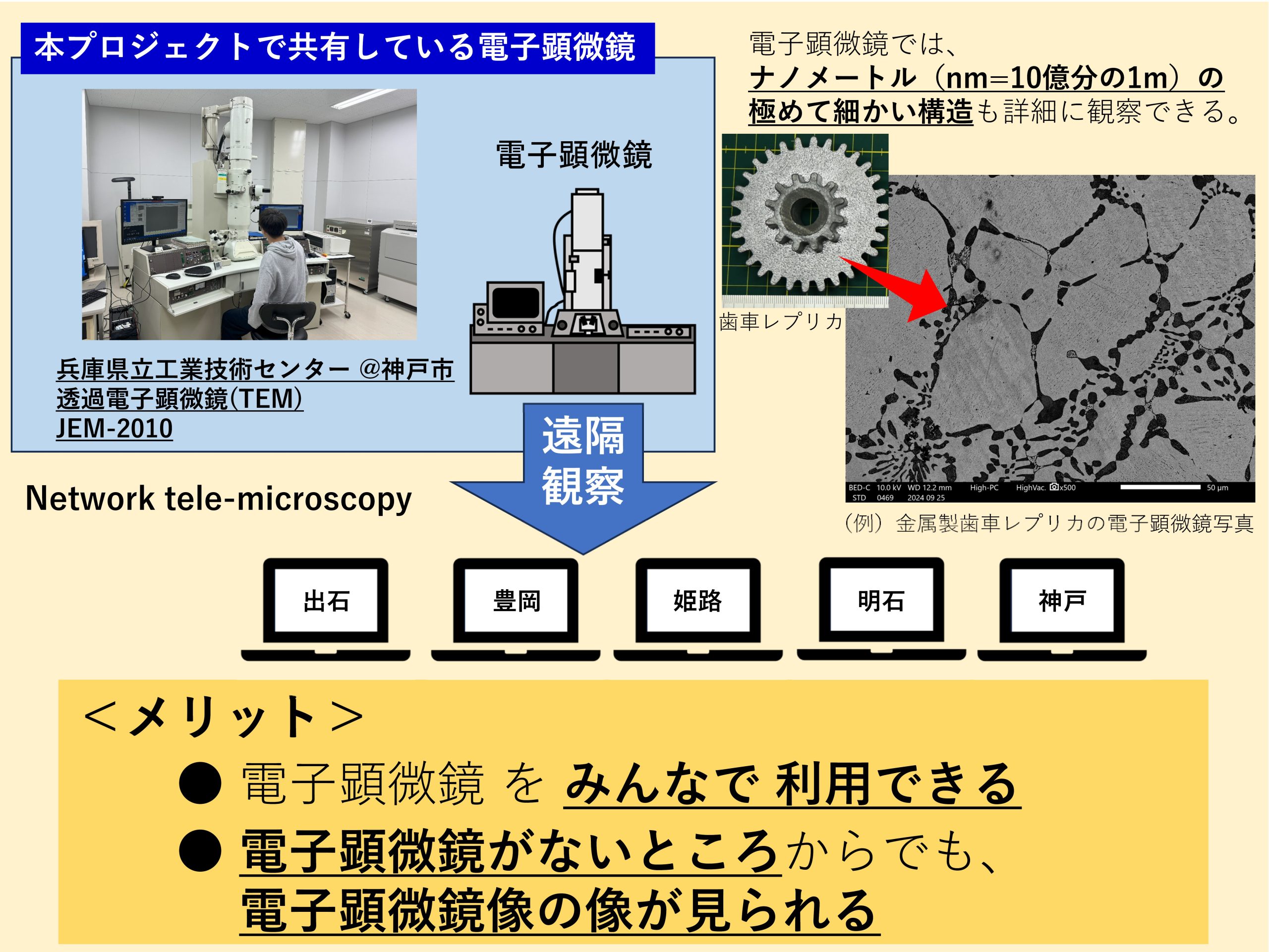コラム:ひょうごメタルベルトcolumn
【学生記事】 明石は、特殊な機械時計を製造できるまちだったのか?〜兵庫県明石市の金属産業の歴史を探ってみた〜

●はじめに
兵庫県立大学大学院工学研究科のT.T.です。私は現在、博士前期課程で、機械学習を使って合金の融点を予測し、新合金を開発する研究を行っています。
「辰鼓楼機械時計・二号機」には、1953年に兵庫県明石市で設計製作されたことを伝える銘板が貼ってありますが、明石市出身の私は、その当時の明石で時計産業が盛んであったという話は聞いたことがありません。なぜ明石という土地で設計・製作されたのか、そして、機械時計の中でも特殊な「大型の機械時計」をどうやって作ることができたのか。この謎は、明石と工業の歴史を解明すればわかるかもしれないと考えました。
明石市は、県庁所在地である神戸市に隣接し、瀬戸内海を挟んで淡路島を眺める、面積約50 km2の小さな町です。そんな小さな明石市ですが、日本標準時子午線上を通るため、「ときのまち」と呼ばれています。名所としては、子午線の上に建てられた大時計が目印の「明石市立天文科学館」、明石港でとれた新鮮な魚介類が並ぶ商店街「魚の棚」などがあります。グルメでは、たこ焼きの源流ともいわれる「明石焼き」が有名です。
●明石と金属産業
明石は、「阪神工業地帯」という古くからの工業地帯と、戦後に新興した「播磨臨海工業地域」との接点という立地で、工業が盛んなエリアです。
「阪神工業地帯」は、大阪から神戸にかけて広がるエリアで、「日本三大工業地帯」の一つに数えられています。かつては日本一の工業地帯といわれ、他と比べて金属産業の割合が高く、多くの中小企業に支えられた工業地帯でした。その歴史は古く、1800年代後半から鉄鋼業、重化学工業、機械工業、繊維工業などが盛んな工業地帯として発展していきました。なかでも大阪・神戸の臨海部では金属工業、機械工業、製薬業を主とした巨大工場と、それに伴う中小工業が発展しました。1900年代前半には、明石や加古川でも大規模工場が新設されるなど、兵庫県の南部でも鉄鋼業が盛んになり、機械工業が発展する土壌が生まれました。
「播磨臨海工業地域」は、明石から岡山県との県境まで広がる工業地域で、戦後の1946年に「工業整備特別地域」に指定されてから鉄鋼業や重化学工業の工場が急速に発展したエリアです。特に高度成長期以降の日本経済を牽引する存在となり、現在も日本有数の工業地域として活躍しています。
このように、兵庫県の瀬戸内海沿岸部では、金属素材の製造・加工に関する企業集積地帯が形成しており、「ひょうごメタルベルト」と名付けられています。
●明石と機械時計
「辰鼓楼機械時計・二号機」が製造された1953年頃は、第二次世界大戦が終結し、日本の工業が再興し始めた時代です。明石にまつわる工業の歴史に関する文献は少なく、不明瞭なことも多いのですが、再び活性化し始める阪神工業地帯の流れと、高度成長期以降に新興する播磨臨海工業地域の土台となる、神戸から西へと寄せる工業化の波によって、明石の工業は発展したと考えられます。このように、明石の周辺には鉄鋼業を強みとする工場の環境が存在したため、大型の精密機器である辰鼓楼の機械時計を加工することができたのかもしれません。
<参考文献>
掛 章孝(2019)『阪神工業地帯の旧中核地域の変化』
竹内 淳彦(1965)『阪神工業地帯の形成-工業構造変化を中心として-』
<執筆>
執筆:T.T.(兵庫県立大学大学院工学研究科・博士前期課程 学生)
サポート:森(ワードワーク), 永瀬(兵庫県立大学)